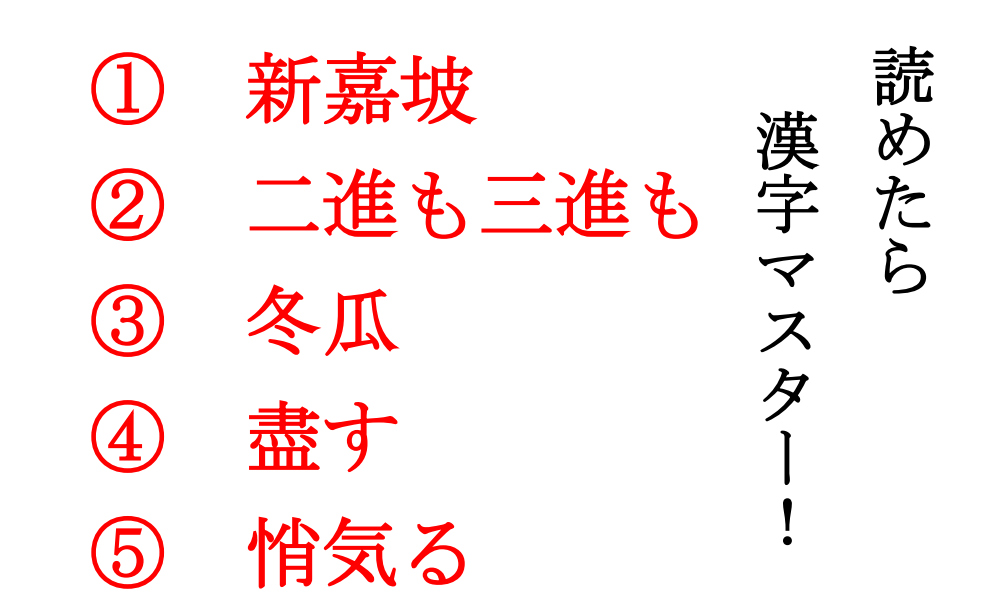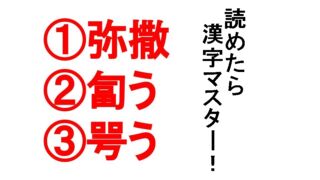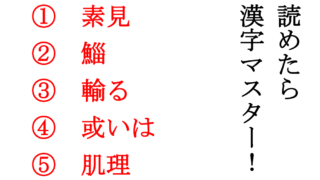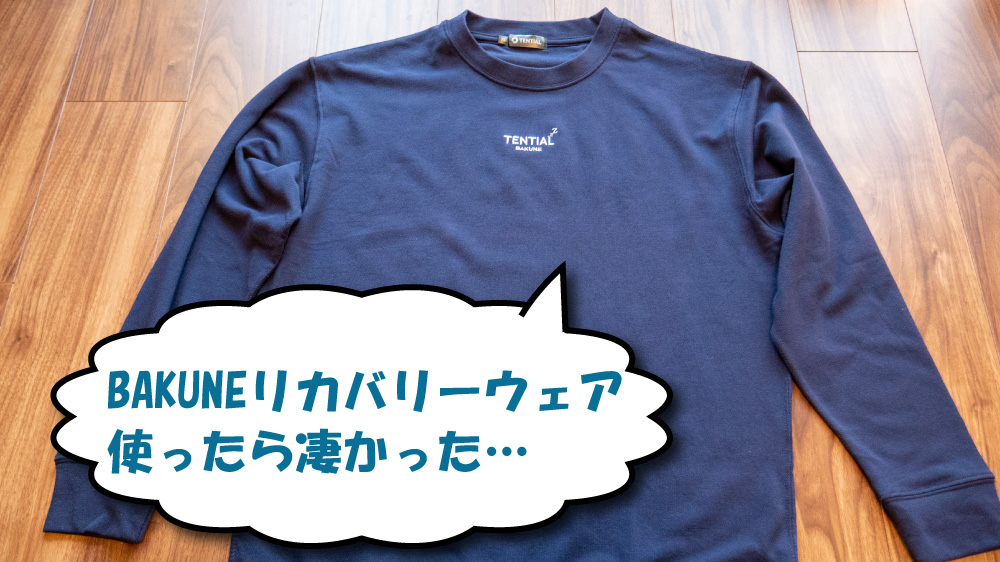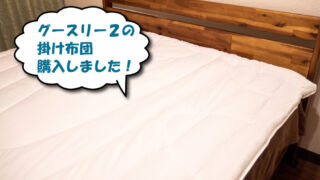今日の難解漢字は、
「新嘉坡」
「二進も三進も」
「冬瓜」
「盡す」
「悄気る」
です!
どれもなんとなく読めそうな漢字ばかりですが、
なんと読むか分かりますか?
目次
1つ目の漢字は「新嘉坡」です!
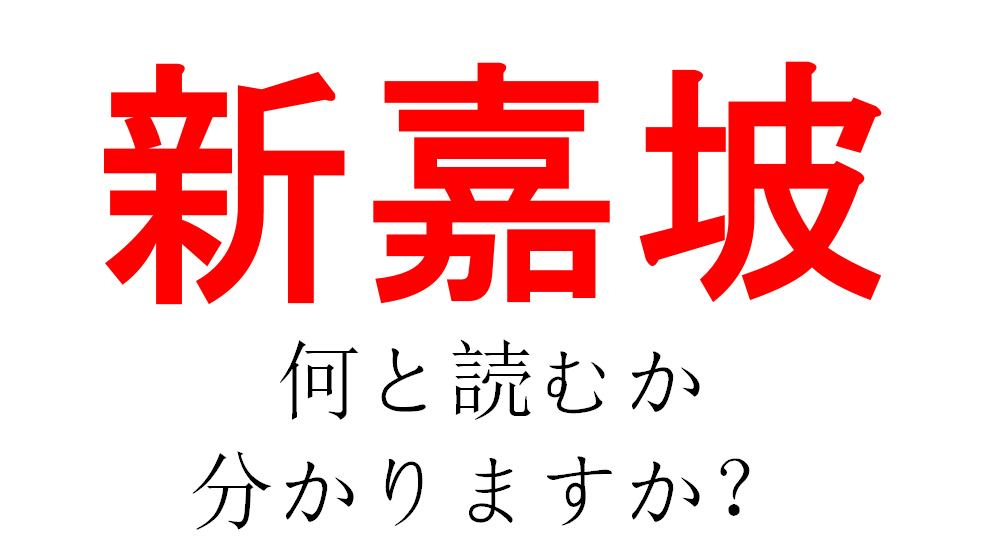
音読みをすれば「しんかば」になりますが、正解には遠すぎます。
字の意味としても「嘉」は「喜ばしい」・「美しい」、「坡」は「土手」や「堤防」のような意味を持ちますが、それに「新」がついても推測が難しいですね。
ヒントに行く前ですが、最初の「新」はそのまま「しん」と読みます。
さぁ、この「新嘉坡」は何と読む?
「新嘉坡」の読み方のヒントはコレ!
ヒント① 通常はカタカナで読み、「シン〇〇ー〇」の6文字です。
ヒント② 東南アジアにある国名です。
ヒント③ 大きなライオンの口から水を吐く像が有名です。
「新嘉坡」の読み方の正解は・・・・?

正解は、「シンガポール」です!
シンガポールと言えば、東南アジアでは貿易・交通・金融の中心地の一つであり、なんと外国為替市場と世界の港湾取扱貨物量で上位2港のうちの1港でもある、そんな経済大国なのをご存じでしょうか。
世界銀行の報告書「ビジネス環境の現状」でも、シンガポールは9年連続で「世界で最もビジネス展開に良い国」に選ばれているほど。
また、日本人の海外旅行先としても人気が高く、セントラル地区にある「マーライオンの像」は有名ですね。
なんでライオンの像があるのかというと、シンガポールはマレー語で「スィンガプラ」。直訳すると「ライオンの町」となることから、この像がシンボルとして置かれているのだとか。
今年の夏はシンガポールに行きたくなってきました・・・。
2つ目の漢字は「二進も三進も」です!

「二進も三進も」
「一進一退(いっしんいったい)」などの印象から「にっしんもさんしんも」と読む方が多いかもしれませんね。
おそらく困った人がこの言葉を使うのを聞いたことがあると思いますが、なんと読むかわかりますか?
「二進も三進も」読み方のヒントは?
ヒントは、物事がうまくいかなくて何もできない様子を表す言葉です。
類語は
「どうにもこうにも」
「行き詰まる」
「身動きが取れない」
などが挙げられます。
「二進も三進も」の読み方、正解は・・・
 正解は・・・
正解は・・・
「にっちもさっちも」
です!
「今月も赤字でもう二進も三進もいかなくて途方に暮れている」
「もう二進も三進もいかなくなってしまった」
のように使います。
進むという漢字を使っているので「進めない」という意味かと思ってしまいますが、実はこの言葉はそろばん用語からきています。
「二進」は2÷2のこと「三進」は3÷3のことで、どちらも答えが1となってすっきりと割り切れます。二進でも三進でもない=割り切れない(勘定が合わない)=商売がうまくいかない・どうにもならないという意味となりました。
それにしても「二進も三進も」いかない状況には極力なりたくないですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
3つ目の漢字は「冬瓜」です!
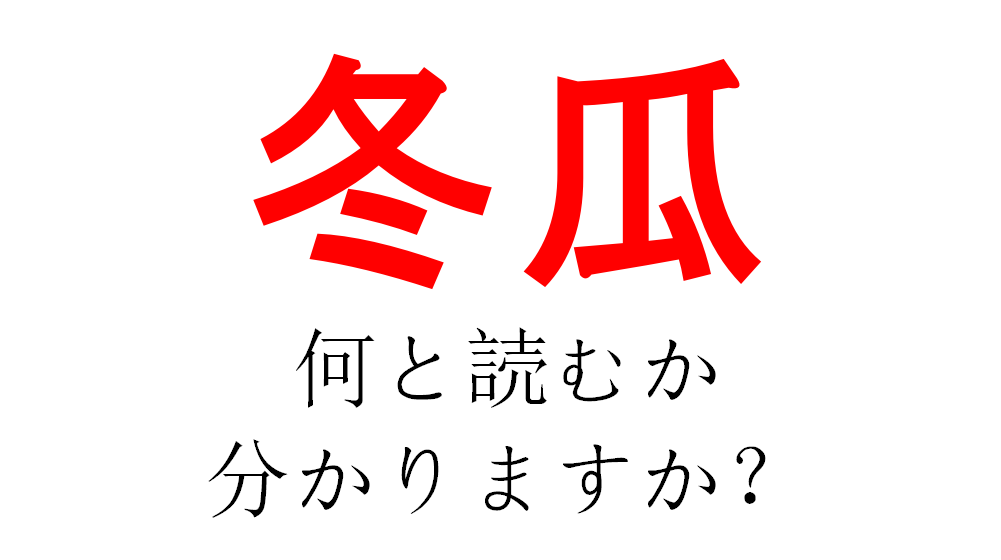
今回の漢字はサービス問題です!
逆に言うと、読めないとちょっと恥ずかしいかも・・・。
知らない人は、ぜひこの機会に読めるようになりましょう!
普段から、スーパーや八百屋で買い物をしている人なら、必ず見たことがある漢字ですので、自信をもって回答してくださいね!
ちなみに「冬瓜」を読めるだけでなく、その姿かたち、いつ買う(獲れる)ものなのかも考えてみてください。
「冬瓜」の読み方のヒントはコレ!
ヒント① 「〇〇〇〇」の4文字です。
ヒント➁ 見た目は大きいキュウリ?ヘチマ?
ヒント③ 「沖縄冬瓜」が有名です。
「冬瓜」の読み方の正解は・・・・?

正解は、「とうがん」です!
「冬瓜」は、「冬の瓜(うり)」と書くことからも、秋から冬に出回る野菜の一つです。
スーパーや八百屋で商品として並ぶのは冬の時期になりますが、「冬瓜」の旬の時期は何と夏なんです!
意外にも、冬の食べ物と認識している人も多いですが、夏に旬を迎える野菜なのに、つるを切らない「玉のままであれば冬まで保存が可能」ということから「冬瓜」と呼ばれるようになったそうです。
いろいろな料理に使われますが、「冬瓜」の約95%は水分という、ほとんど栄養もない野菜にありますが、その変わりにカロリーはめちゃくちゃ低いんです!
これはダイエッターにとっては外せない、あらたな救世主の到来ですね!
4つ目の漢字は「盡す」です!
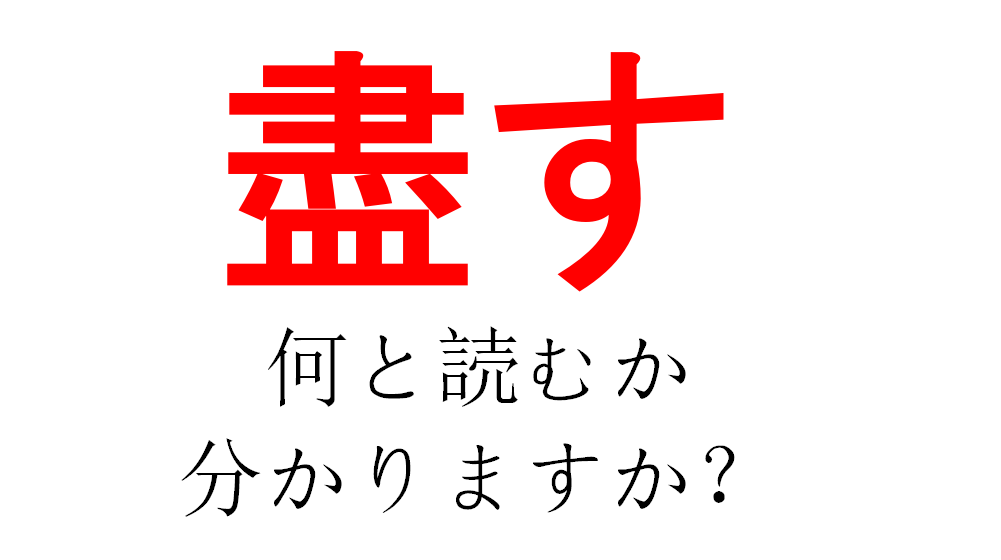
はい、もういきなり読めません。
我儘を言わせてもらうと、辞典で調べたいくらい。そんな「我儘」の「儘」に似ているから「まます」?くらいしか思いつきません・・・。
あるいは、「臭い物に蓋をする」の「蓋」にも似ているから、「ふたす」??
ここまで手も足も出ない問題なら、もうヒントを見るしかありません!
「盡す」の読み方のヒントはコレ!
ヒント① 「〇〇す」の3文字です。
ヒント② これは「尽」と同じ意味を持ちます。
ヒント③ 最初の文字は「つ」です。
「盡す」の読み方の正解は・・・・?

正解は、「つくす」です!
え?「つくす」って「尽くす」じゃないの?と思ったあなたは正解です!
「盡」という漢字は、「尽」の旧字体であり、人名に使われるときの漢字でもあります。
意味は「すべて使い果たす」「なくなる」というもので、「尽」と同じなので音読みにしても「じん」になります。
ここで面白いところは、旧字体で表しただけなのに「尽くす」⇒「盡くす」とはならずに、「盡す」と送り仮名の使い方が違うところなので、使うときは気をつけましょう!
5つ目の漢字は「悄気る」です!
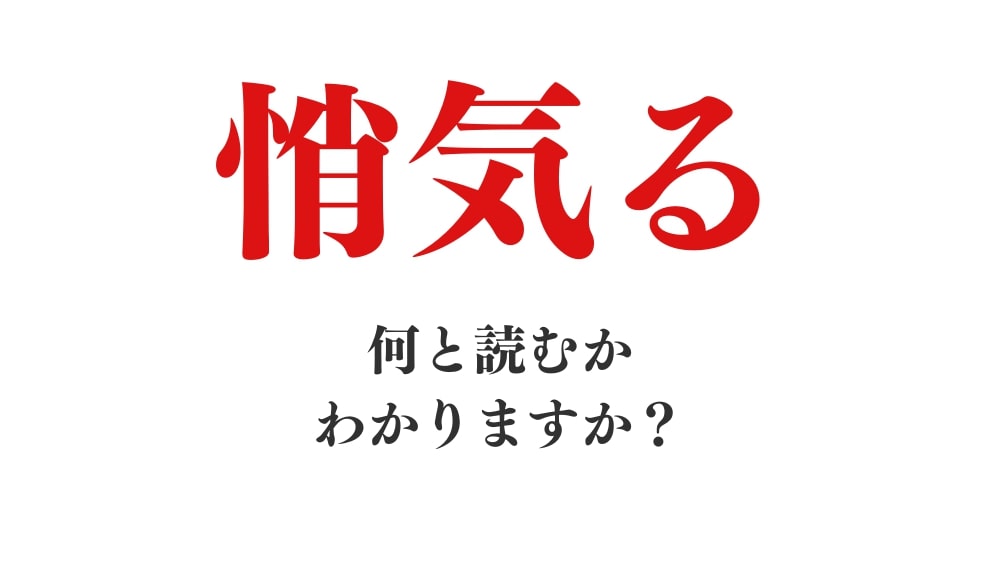
「悄気る」
これ、何と読むかわかりますか?
普段の会話や、歌詞でも使われている、
聞き馴染みのある言葉なのですが…
さあ、あなたは何と読みましたか?
「悄気る」読み方のヒント!
なんとなく雰囲気で読めた!という方もいるのでは?
わからない…という方へのヒントは
「悄」は「しょう」という音読みを持っています。
でも「しょうきる」ではないですよ!
さて、読めましたか?
「悄気る」の読み方、正解は…
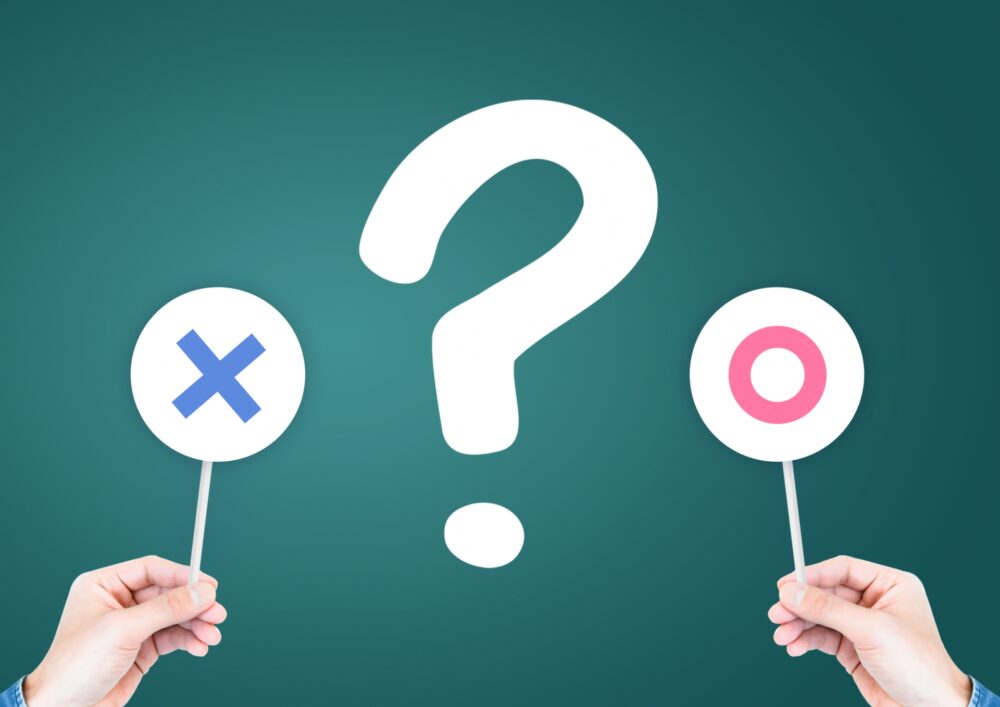
気になる正解は…
「しょげる」
です!
「悄気る」は、
「がっかりして元気がなくなる」「しゅんとする」などの様子を表す言葉。
普段の会話でもよく聞く言葉ですよね。
「友人が失恋して悄気ている」
「仕事で失敗して悄気る後輩を慰める」
など、使いどころが多い言葉です。
あまり見慣れない「悄」は、
憂いに沈んでしおしおとして力のない様子や、
意気消沈した様子を表した漢字です。
そんな漢字が使われているから
「悄気る」という言葉も、
しょんぼりした様子を表す言葉になっているんですね。
ちなみに「悄」は漢字検定1級の漢字。
しかも「悄気る」は本来の読み方をアレンジした言葉。
読めた方は自信を持ってOK!
もし間違えてしまっても、
悄気ずに今日から正しく読みましょう!
まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございました!