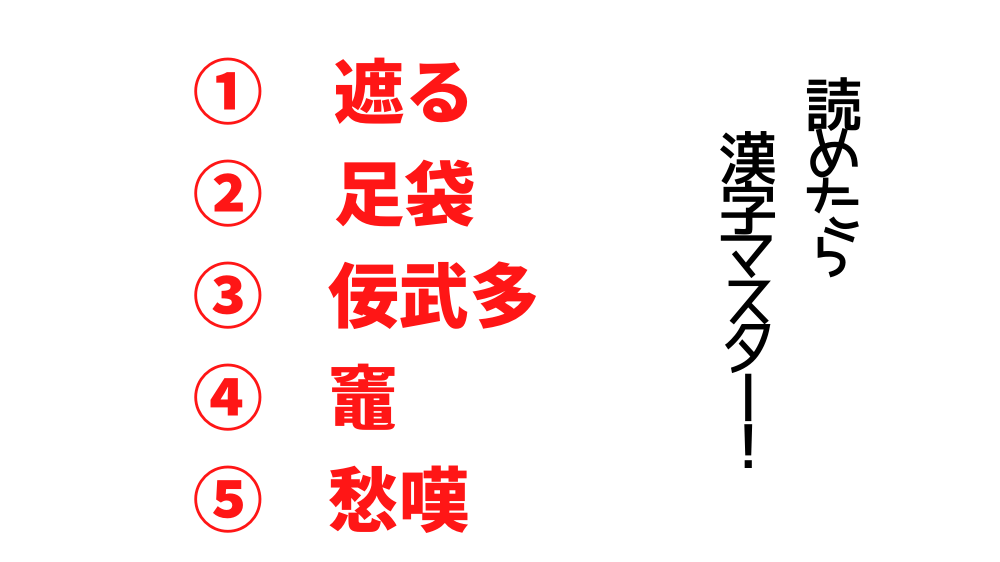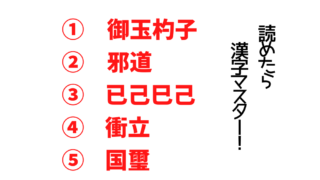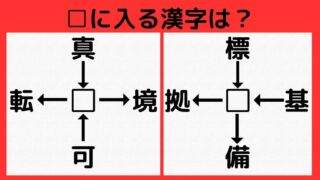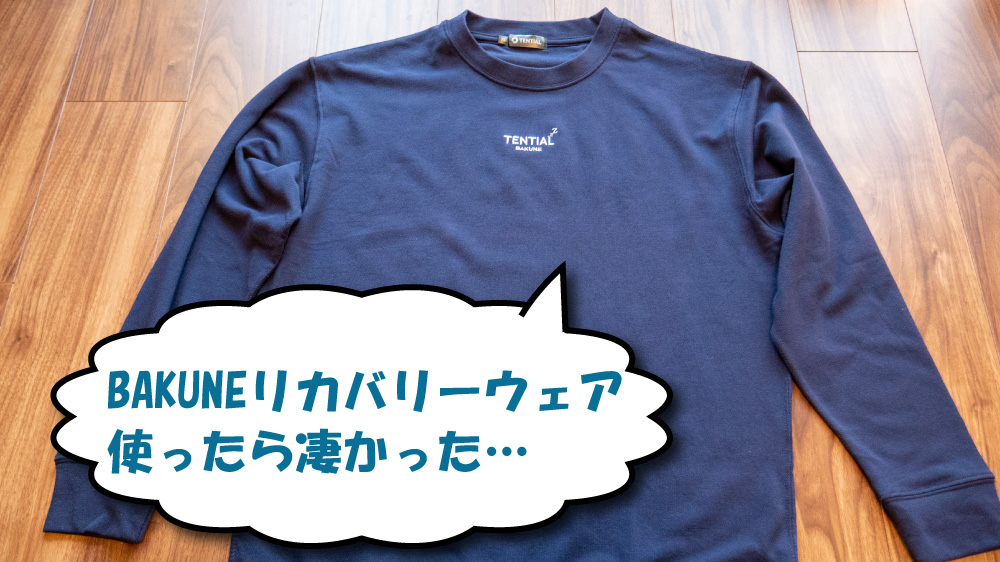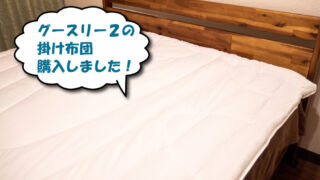今日の難解漢字は
「遮る」
「足袋」
「佞武多」
「竈」
「愁嘆」
です!
どれもなんとなく読めそうな漢字ばかりですが、
なんと読むか分かりますか?
目次
1つ目の漢字は「遮る」です!
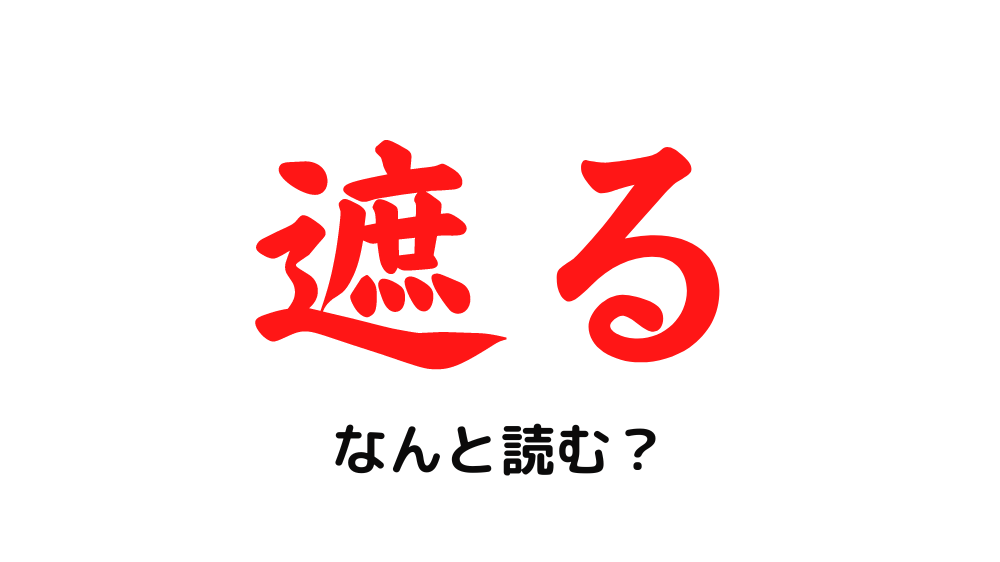
「遮る」と書いて、なんと読むか分かりますか?
遮断機の「遮」ですが、もちろん(しゃる)ではありません。
邪魔をされると腹が立ちますが、ムカつくと邪魔をしてしまうアレの事です。
感情だけではなく、真夏の暑さを「遮る」すだれやよしずなんかにも使いますね。
色々な使われ方をしますが、さて、「遮る」と書いてなんと読むでしょうか?
「遮る」読み方のヒントは?
「遮る」は、誰かが勝手に行動しないように、進行や行動を邪魔して辞めさせることです。
発言を遮ったり、行動を遮ったり。
誰かにイチイチ遮られたら腹が立ちますが、ムカつく時には誰かの行動を遮ります。
他にも、広いフロアについたてを置いて遮るなんて使い方もできます。
真夏の日差しが部屋に入り込まないように、よしずやすだれ、グリーンカーテンなんかで遮る事もありますね。
「遮る」読み方のもうひとつのヒントは?
ひらがなにすると「〇〇〇る」です。
さて、もうわかりましたか?
「遮る」の読み方、正解は・・・

正解は・・・
「さえぎる」
です!
遮るものがあれば、取り除きたいと思うのが人間の本能でしょう。
くれぐれも人の行動を遮る時には注意しましょう。
2つ目の漢字は「足袋」です!
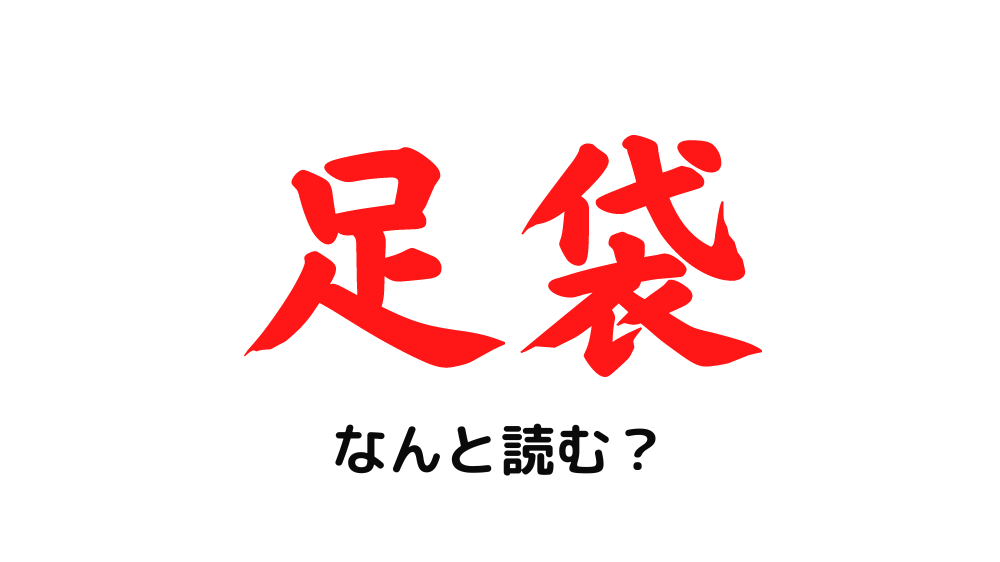
「足袋」と書いて、なんと読むか分かりますか?
足の袋という漢字から、すぐに答えが分かった人も多いのではないでしょうか?
そう、アレの事です!
さて、「足袋」と書いて、なんと読むでしょうか?
「足袋」読み方のヒントは?
今でいう所の、靴下の事で正解です!
着物を着る時の靴下の事です。
普通の靴下と違う事は、伸びない事、それに足の先がふたつに分かれていることです。
草履を履くことが前提で作られているので、足袋の足先も分かれています。
最近はこの足先が分かれているのが健康にいいとか、足が蒸れないとか、足裏に力が入るので腰にも優しいとかいわれて流行っているようで、靴下タイプだけでなく、足袋シューズといった靴にもなっています。
確かに5本指の靴下が流行った時に、なかなか快適であったことを考えると履き心地もいいのかも。
ひらがなにすると「〇〇」です。
もうわかりましたか?
「足袋」の読み方、正解は・・・

正解は・・・
「たび」
です!
ちなみに足袋の留め具は「こはぜ」といいます。
このこはぜで足袋がしっかりと留まるなんて、感心しますね!
3つ目の漢字は「佞武多」です!
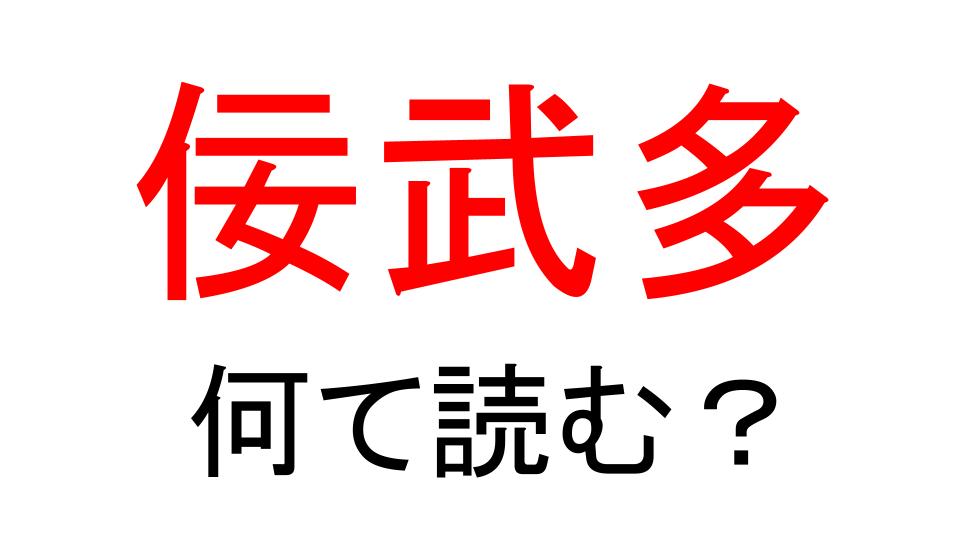
今回の難読漢字クイズは「佞武多」です。
あるエリアに住んでいる人なら、簡単にわかるはず!
さて、あなたは何と読みますか?
「佞武多」の読み方のヒントは?
1.らっせらー!やーやどー!やってまれー!
2.「佞武多」の「武」は「ぷ」とも「ぶ」とも読みます。
3.『蚤の乗る船の事は、正月の宝船の古い形式・奥州の佞武多など』折口信夫「とこよ」と「まれびと」と より引用
正解は…
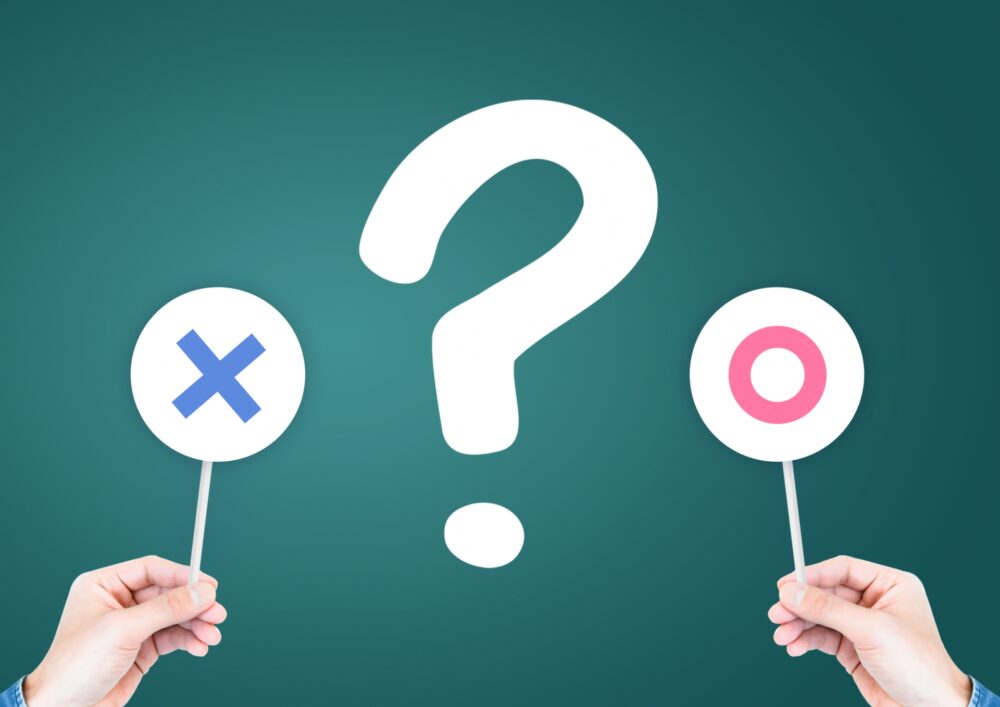
正解は「ねぶた」または「ねぷた」でした!
どちらの読み方も正しいです。
発音の違いは地域ごとの訛り、漢字は当て字です。
青森県の有名なお祭りですね!
青森市は「ねぶた」、掛け声はらっせらー!
弘前は「ねぷた」、掛け声はやーやーどー!
五所川原市は「立佞武多(たちねぷた)」、掛け声はやってまれー!
「佞武多」の語源
「佞武多(ねぶた・ねぷた)」の語源には複数の説があります。
そのうち有力なのが柳田国男「眠流(ネブリナガシ)考」を基にした説。
「眠り流し」とは、眠たいこと、つまり睡魔を追い払う行事です。
暑い夏のだるさを払う意味で行われたのだそう。
具体的な「眠り流し」の行事は…
- 水浴びをする
- 形代(かたしろ)を灯篭や笹竹に乗せて川や海に流す
- 合歓木(ねむの木)を川や海に流す
- 髪や硯(すずり)を洗う
予約が大変そうですが、一度は見てみたいお祭りです!
4つ目の漢字は「竈」です!

「竈」の読み方をご存じでしょうか?
昔の言葉では「へっつい」とも読みますが、今回はそれ以外の読み方を正解とします。
さて、何と読むのか…
あなたにはわかりますか?
「竈」の読み方のヒントはこちら
- ひらがなで書くと「〇〇〇」の3文字です
- 「鬼滅の刃」の主人公の名前は?
- 「へっつい」を今の言葉でいうと…
以上の3つのヒントから考えてみてくださいね。
「竈」の読み方!正解は!?

正解は「かまど」です!
「竈(かまど)」とは、鍋や釜の下で火をたいて調理するための設備で、
ガスが一般家庭に入る前に使われていたものです。
アニメ「鬼滅の刃」の主人公の名前は「竈門炭治郎(かまどたんじろう)」にも「竈」の字が使われているため、すぐにわかった人も多いのでは?
また、昔はかまどのことを「へっつい」と呼んだので、「竈」は「へっつい」とも読めます。
「かまど」の漢字表記には他にも「竃」や「釜戸」がありますが、「竈」と書かれることが最も多いようです。
5つ目の漢字は「愁嘆」です!
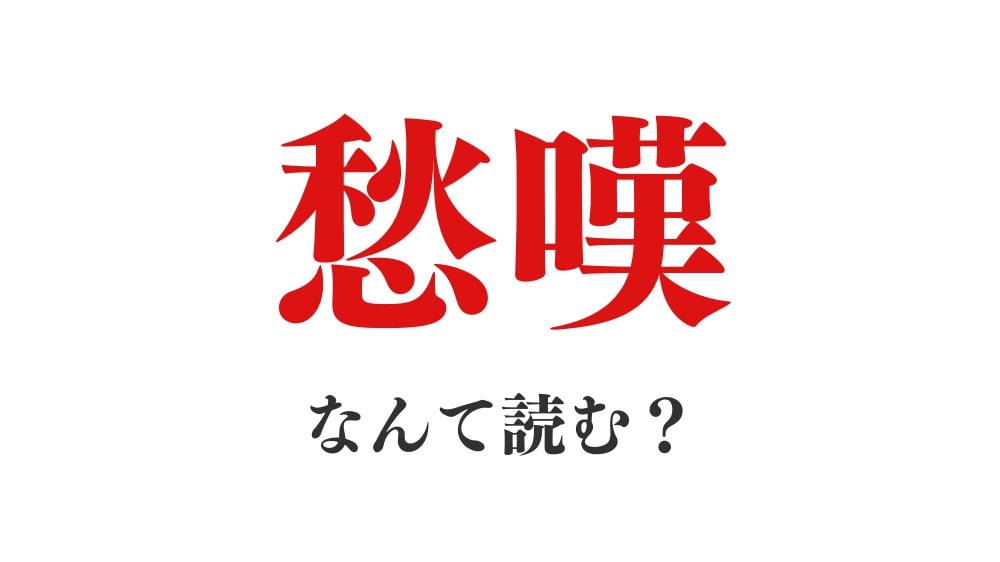
「愁嘆」
これ、何と読むかわかりますか?
使われているどちらの漢字も、なんとなく悲しげな印象のこの言葉。
さあ、あなたは何と読みましたか?
「愁嘆」読み方のヒント!
「愁嘆」は、漢字の読み方としてはとても簡単です!
漢字の読み方のルールがわかっている方なら、すぐに正解できてしまうかも。
ちなみに「あきたん」ではありませんよ!
さて、あなたは何と読みましたか?
「愁嘆」の読み方、正解は…
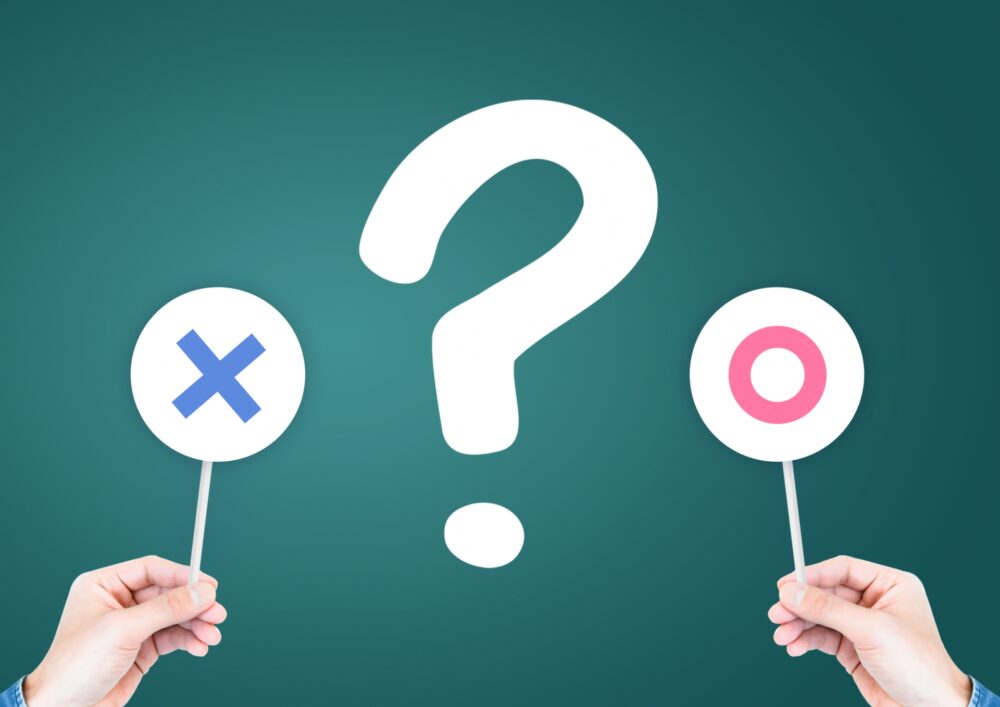
気になる正解は…
「しゅうたん」
です!
「愁嘆」は、
「うれえなげき、悲しむこと」という意味の言葉です!
「愁」には「うれえる、悲しむ、思いなやむ」といった意味があります。
「憂愁」や「ご愁傷さまです」という言葉にも使われていますよね。
「嘆」には「なげく、ため息をつく」といった意味があります。
「嘆願する」などで使われますね。
ただし「嘆」は、いい意味で使われることもしばしば。
「感嘆の声が漏れる」などでは、「素晴らしすぎてため息が出る」
というニュアンスで使われます。
「愁嘆」は、悲しみ嘆く様子がうかがえる漢字。
同じ意味の感じを重ねて、意味を強調させています。
この漢字を使う場面がないに越したことはないのですが……
知識として知っておいて損のない漢字です。
これを機にスマートに読めるようになりましょう!
まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございました!