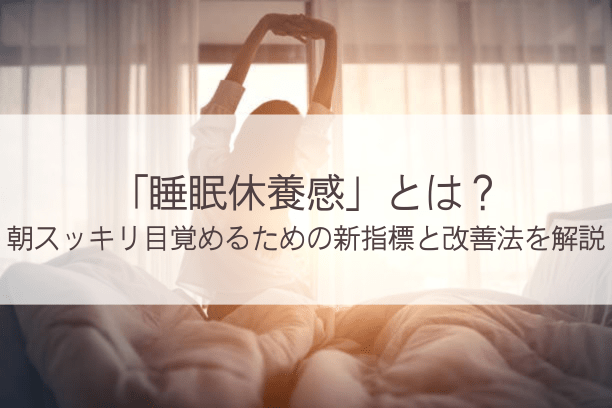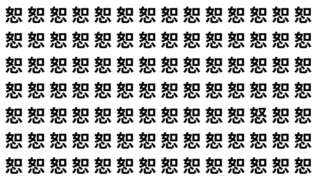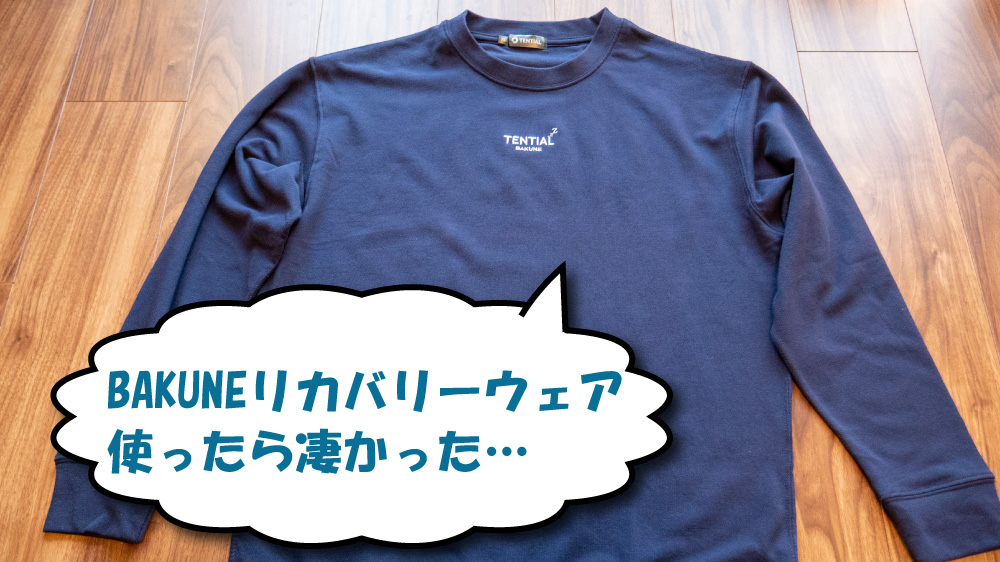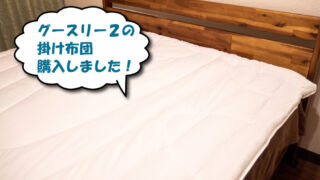「しっかり寝たはずなのに、なぜか疲れが残っている……」
そんな経験はありませんか?
それはもしかすると、あなたの「睡眠休養感」が低下しているサインかもしれません。
この記事では、近年注目されている睡眠の新たな評価指標「睡眠休養感」について、基本的な解説から改善のための具体的な方法までをわかりやすく紹介します。
睡眠休養感とは?
「睡眠休養感(すいみんきゅうようかん)」とは、睡眠によってどれだけ心身の疲れが取れたと感じられるかという主観的な感覚を示す言葉です。
従来、睡眠の評価は「睡眠時間」や「中途覚醒の有無」など客観的なデータが中心でした。しかし、近年ではそれだけでは不十分だとされており、「質の良い睡眠=休養できたという実感」が重視されています。
厚労省も注目する「睡眠休養感」
睡眠による休養感(睡眠休養感)が得られている人は健康意識が高く、日中のパフォーマンスも良好である傾向がみられます。(健康づくりのための睡眠ガイド2023)
睡眠休養感が低いとどうなる?
「しっかり寝たのに眠い」「日中の集中力が続かない」などの症状は、睡眠時間ではなく休養感の欠如が原因かもしれません。
慢性的な疲労・倦怠感
睡眠休養感が低いと、体力や精神力の回復が不十分となり、慢性的な疲労感につながります。これは長期的にはメンタル不調や生活習慣病リスクの上昇にも関係します。
生産性の低下と事故リスク
日中の注意力・判断力が低下することで、業務効率の悪化や交通事故、作業ミスのリスクが高まります。
睡眠時間だけでは測れない
同じ7時間睡眠でも、「ぐっすり寝た」と感じる人と「なんだか疲れが残る」と感じる人がいるように、“質より実感”が大事なのです。
睡眠休養感を高める5つの習慣
ここからは、睡眠休養感を高めるための具体的な生活改善ポイントを紹介します。
1. 起床・就寝時間を整える(体内時計のリセット)
- 毎日同じ時間に起きる
- 朝はカーテンを開けて日光を浴びる
2. 寝室環境を整える
- エアコンで室温は20〜25度をキープ
- 遮光カーテンやアイマスクを活用
- 寝具を見直す(マットレス・枕)
3. 夕方〜夜の過ごし方を見直す
- カフェインの摂取は15時までに
- スマホ・パソコンの使用は就寝1時間前には終了(ブルーライト回避)
- 軽いストレッチや入浴で副交感神経を優位にする
4. 寝る前のルーティンを持つ
- ホットドリンクを飲む
- 瞑想や深呼吸でリラックス
- アロマで香りから入眠スイッチを入れる
5. 朝食と軽い運動を習慣化する
「起きたらすぐ朝日を浴びて、朝食を食べる」ことが、体内時計をリセットし、夜の快眠へつながります。
睡眠休養感を測るには?
客観的な数値では測りづらい「休養感」ですが、以下の方法で自己評価が可能です。
厚労省のチェックリスト
「睡眠による休養が十分に取れていますか?」という問いかけに対して、
- はい
- いいえ
- わからない
といった簡単な選択で自分の状態を見直すことができます。
スマートウォッチ・アプリの活用
Oura RingやApple Watch、睡眠アプリ(Sleep Cycleなど)では、睡眠スコアや覚醒回数を測定し、自分の“眠りの質”を可視化できます。
快眠をサポートするおすすめアイテム
マットレス・枕
- 体圧分散性が高いウレタン系マットレス(NELL、モットンなど)
- 首のカーブに沿った高低差のある枕
アロマ・間接照明
- ラベンダー・ベルガモットなどリラックス効果のある香り
- 明るすぎない暖色系ライト
リカバリーウェア・サプリ
- 睡眠用リカバリーウェア(BAKUNEなど)
- サプリメント
※使用する際は体質や薬との相互作用に注意しましょう。
まとめ|睡眠休養感は“実感”がカギ!
「何時間寝たか」よりも「どれだけ休めたか」が、これからの睡眠の指標です。
- 日中に眠気や不調を感じたら、睡眠休養感を見直すサイン
- 習慣の見直しで、睡眠の質と満足度を向上させられる
- 自分の眠りを知ることから始めよう
今日からあなたも、“本当に疲れが取れる睡眠”を手に入れてみませんか?